「紙のチラシは、環境に悪いのでは?」
広告業やポスティング事業に携わっていると、そんな声を稀に耳にすることがあります。
「チラシをポスティングするという広告手法は、エコではないのではないか」
とりわけSDGsに積極的に取り組む企業は気になる問題ですよね。
紙=森林伐採、インク=化学物質、そしてポストに投函されてもすぐに捨てられる――。
確かにチラシは、一昔前まではそのようなイメージを抱かれても仕方のない側面がありました。
しかし、近年はチラシの印刷業界も大きく変わりつつあります。
再生紙の活用や森林認証制度の普及、植物由来のインクの登場など、環境負荷を抑える仕組みが広がっています。
さらに、ポスティングという配布手法そのものも地域密着型であり、無駄な物流を伴わない点で、実は環境に優しい側面を持っています。
今回は「紙媒体=エコではない」という思い込みを解きほぐしながら、SDGs時代におけるポスティングの価値を見直してみたいと思います。
【この記事でわかること】(約5分で読めます。)
- 近年の紙広告の実情や最新印刷技術についてわかる
- デジタル広告が普及する今もなお、紙の広告が持つ強みについてわかる
- エコや資源の使い方を意識したポスティングのあり方についてわかる

紙媒体の環境問題への誤解と現実
まず、「紙=環境破壊」というイメージの背景には、森林伐採の問題があります。
確かに、無秩序な伐採が世界の森林を脅かしてきた歴史は否定できません。
ですが、近年の印刷用紙は持続可能な森林管理のもとで生産されるケースが増えており、実際には「伐採したら必ず植林する」というサイクルが機能しています。
代表的なのが、FSC認証紙やPEFC認証紙です。
これらは国際的な森林認証制度で、適切に管理された森林から調達された木材を使った紙であることを示します。日本の大手印刷会社や製紙会社もこの用紙を積極的に導入しており、環境に配慮した広告媒体を求める企業から選ばれています。
また、印刷インクも大きく変わりました。従来の石油系インクに比べて、植物油を原料にしたベジタブルインクが普及し、CO2排出量を大幅に削減。さらにリサイクル時の分離性にも優れており、資源循環を促進しています。
こうした業界の進化によって、紙チラシ=環境負荷が大きいという常識は、すでに過去のものになりつつあるのです。
チラシの配布方法から見るエコ性
次に、チラシの配布の仕組みそのものを考えてみましょう。
新聞折込でのチラシの配布は、広く一斉に届ける仕組みとして効果的。
しかしその分、ターゲットとは異なるエリアや層にまで届き、無駄が発生しがちです。いくらエコな方法でチラシを作成していても、無駄なチラシが発生していればそれはエコとは反してしまいます。
これに対してポスティングは、細かいエリア選定や居住形態(戸建・集合住宅)を選んで配布できるのが大きな特徴です。
たとえば「半径2km以内の住宅を中心に」「子育て世帯が多いエリアに限定」といったターゲティングが可能であり、主に必要な人に情報を届けられます。これは広告効率だけでなく、無駄な印刷や廃棄を減らすという意味で環境にも優しいアプローチと言えます。
さらに、配布エリアが特定の地域に限定されるため、トラックで全国に輸送するような大規模な物流は不要です。印刷所から地域内の拠点に運び、そこから配布員が徒歩や自転車で投函するケースが多いため、輸送時のCO2排出が最小限に抑えられます。
「必要な情報を、必要な場所へ、最短距離で届ける」。これこそポスティングの持つエコな側面と言えるでしょう。

デジタル広告も環境負荷ゼロではない
「それなら、紙ではなくデジタル広告を使えばいいのでは?」と考える方もいるでしょう。
確かにインターネット広告は紙を使わないため、森林資源を消費しません。しかし、デジタル広告も目には見えない環境負荷を抱えています。
その正体は、データセンターの電力消費です。
広告の配信にはサーバーが稼働し続ける必要があり、世界中のデータセンターは膨大な電力を消費しています。国際エネルギー機関(IEA)の試算によれば、インターネット関連の電力消費は世界全体の数%を占める規模にまで拡大しており、今後さらに増加が見込まれています。
つまり、紙もデジタルも、環境負荷がゼロではないという点では共通しています。
大切なのは、媒体そのものを否定するのではなく、いかに環境配慮を取り入れながら活用するか。
ポスティングもその一つの解であり得るのです。
ポスティングをSDGsに活かす方法
では、具体的にポスティングをSDGs対応型広告として活かすにはどうすればよいのでしょうか。
まずは紙選びです。再生紙やFSC認証紙を積極的に使用することで、「環境配慮しています」というメッセージを企業姿勢として打ち出せます。印刷会社はもちろん、大手ネットプリントサービスでも、環境に配慮した用紙を選択することができます。
次に印刷インク。ベジタブルインクや水なし印刷など、環境に優しい印刷方式を採用することで、広告のエコ度を高められます。大手印刷会社はこれを標準仕様として取り入れているケースも増えています。
これらのこだわりを、チラシのデザインに組み込むことも効果的です。
FSC 森林認証マークを付ければ、環境を配慮した印刷であることもアピールできます。
FSC®マークは、FSC®認証紙を使用した印刷製品に簡単に付けることができます。また、FSC®マークにはライセンス番号が入っているため、印刷製品にFSC®マークを付ける場合は、FSC®認証を取得している会社で印刷・加工する必要があります。詳しくは印刷会社にお問い合わせください。
マークを付ける以外にも、「このチラシは環境に配慮した紙とインクで印刷されています」と明記したり、リサイクルを促す一文を添えたりするだけでも、企業のイメージアップにつながります。
さらに、ポスティングは地域と直結しているため、SDGsの目標「住み続けられるまちづくりを」に直結します。地域住民に役立つ情報を提供しながら、環境にも配慮する広告活動――。それは単なる宣伝を超えて、企業と地域社会をつなぐ取り組みになるのです。
まとめ
「紙のチラシ=環境に悪い」というイメージは、すでに時代遅れになりつつあります。
再生紙や植物由来インクの普及、ターゲティングによる効率的な配布、デジタルにも存在する環境負荷――。こうした事実を踏まえると、チラシのポスティングはひと昔前とは違う、むしろSDGs時代に適した広告手段ともいえるのではないでしょうか。
今後は、単に「売上を伸ばすためのチラシ」から、「環境に配慮しながら地域に貢献するチラシ」へと進化していくことが期待されます。企業の信頼を高め、地域住民との関係を深める手段として、サステナブルな広告手段〝ポスティング〟に取り組んでみてはいかがでしょうか。
記事作成会社
株式会社リック 1989年静岡県で創業。広告代理業を礎に自社媒体・自社ポスティング組織を構築。
自社発行の情報誌mydo(マイドゥー)は35年以上に渡り毎月46.5万世帯にポスティングしている。
静岡県のポスティングにおいては100万部を超える配布網を築いており、県内随一のポスティング手配力。現在はWEBマーケから情報誌制作・ポスティングまでのオンライン・オフライン広告を自社で行う課題解決型の広告会社として、静岡県内でも稀有な存在。株式会社リック
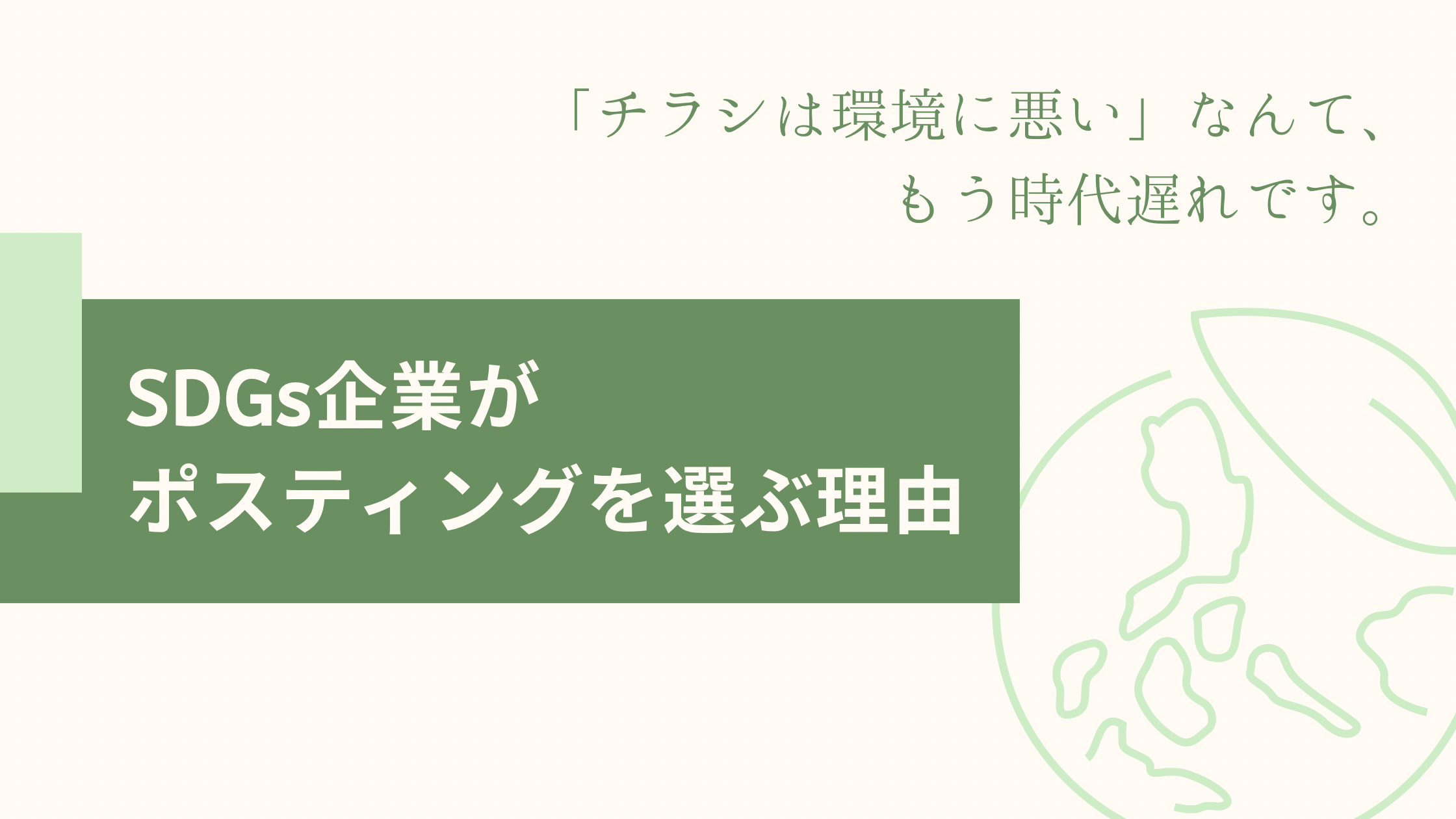
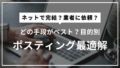
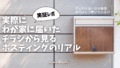
コメント